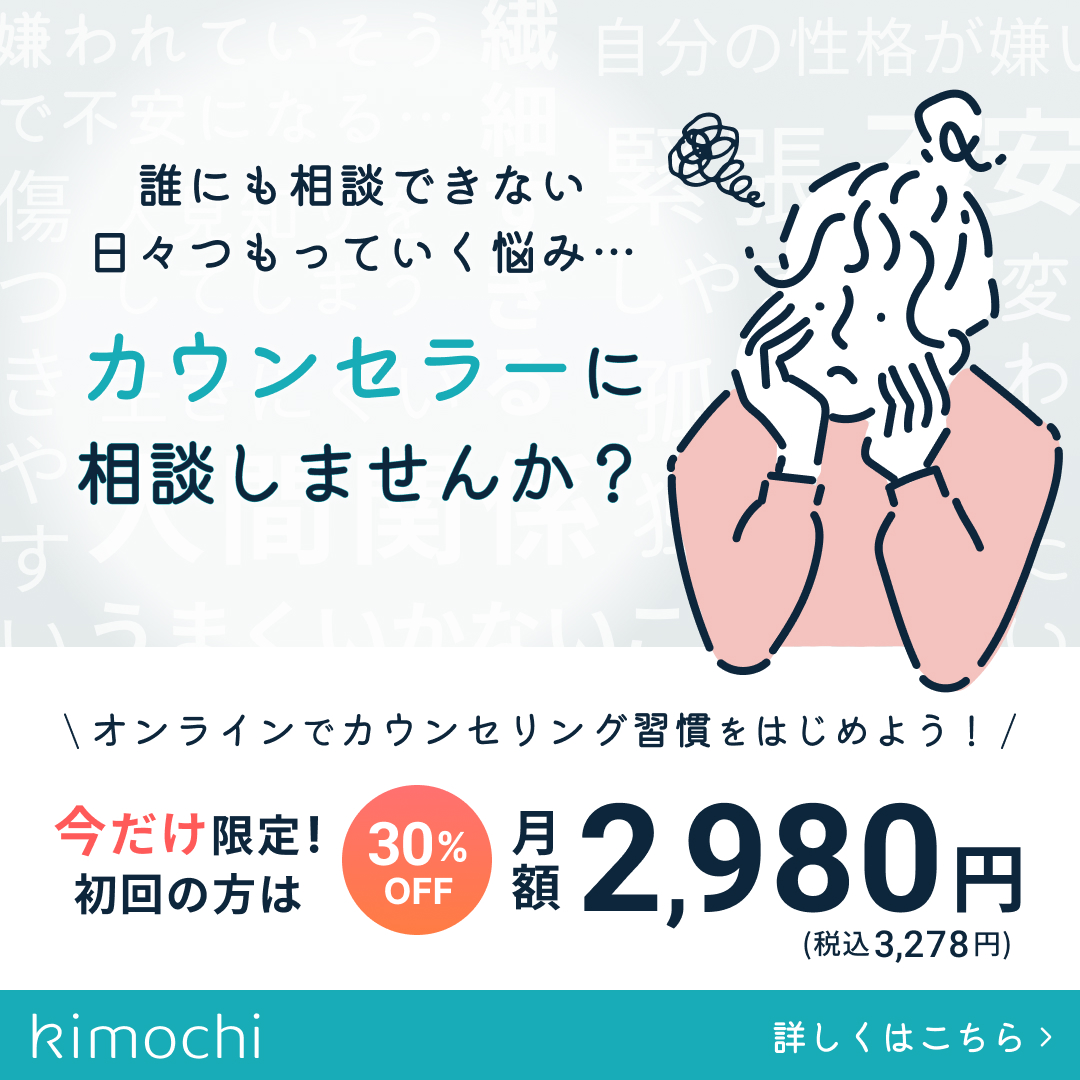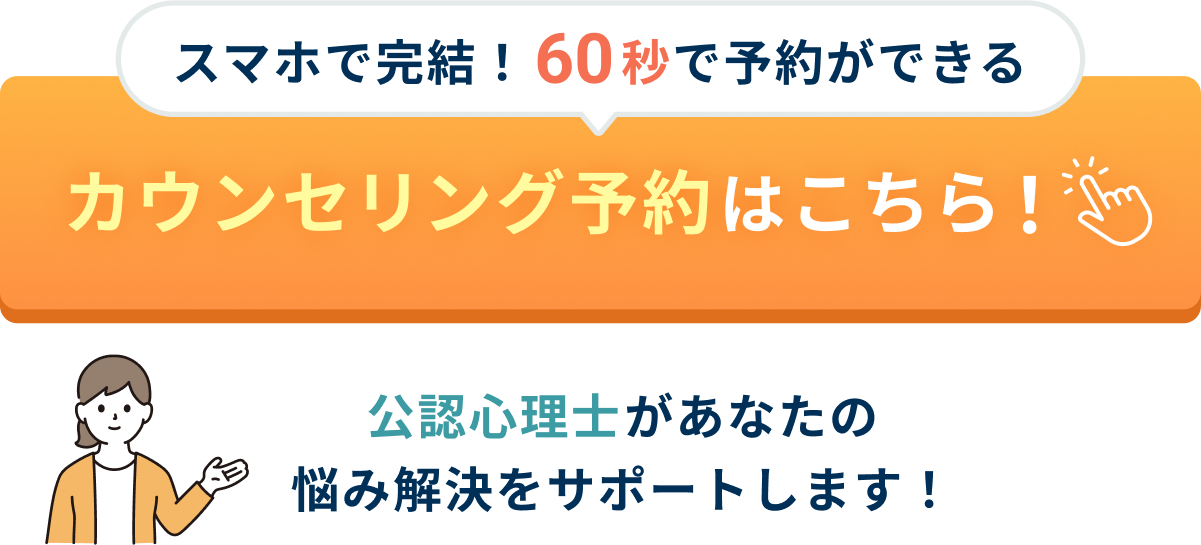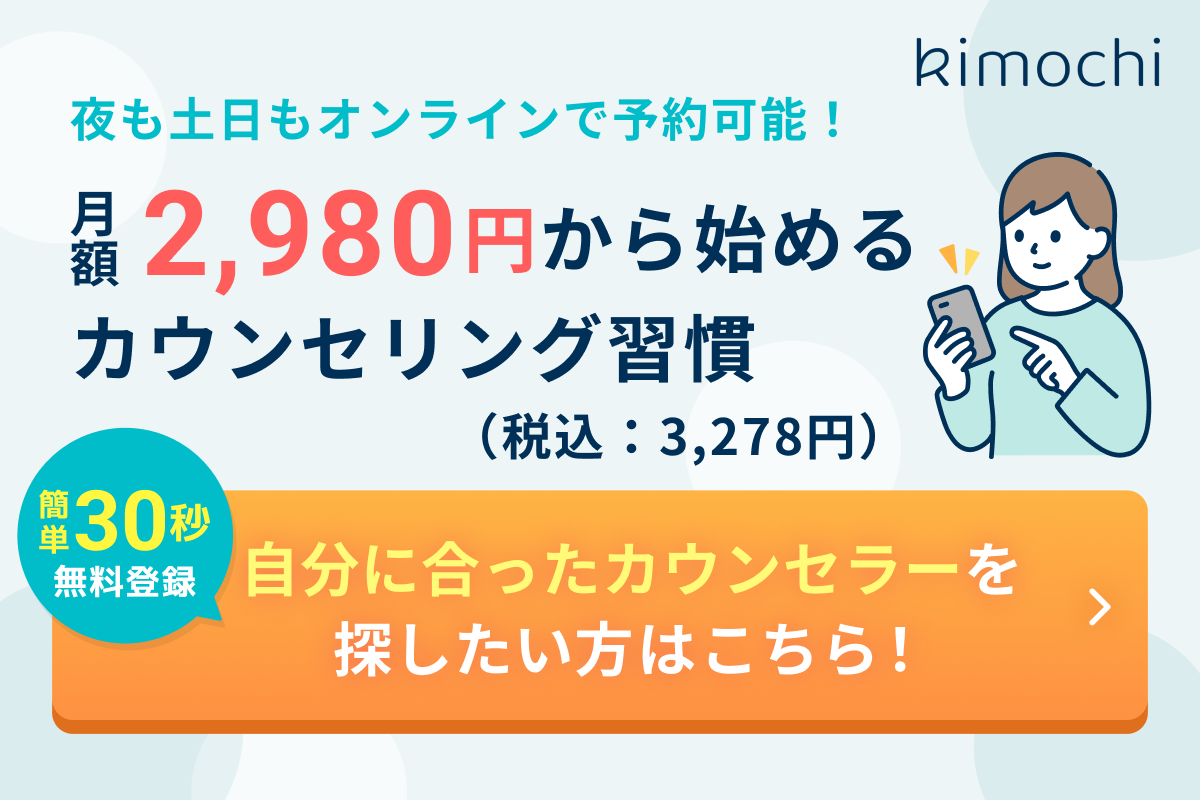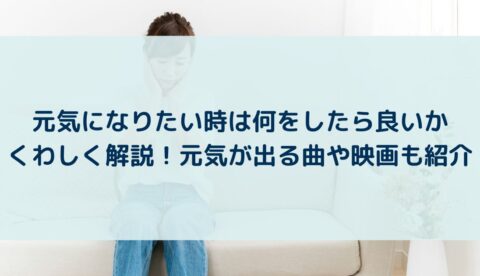「子離れしたいけどなかなかできない」
「いつまでも子どものことが気になってしまう」
このように子離れできずに悩んでいませんか?いつまでも子離れできずにいると、子どもの将来にさまざまな問題が生じるでしょう。
そこで本記事では、子離れについて以下の内容を解説します。
- 子離れできない親の特徴
- 親が子離れできないことで生じる問題
- 親が子離れできない原因
- 子離れできない親が意識すべきこと
この記事を読めば、子離れできないと生じる問題や子離れするために意識すべきことがわかります。ぜひ最後までお読みください!
子離れとは?まず知っておきたい基本
「子離れ」とは、子どもが精神的・経済的に自立し、親が必要以上に干渉せずに見守る状態を指します。
子どもが成長しても親が過度に関与すると、子どもの主体性や自立心の成長が妨げられることがあります。親子関係を健全に保つためには、親自身が子どもの独立を受け入れることが重要です。
子離れできない親の特徴

子離れできない親の特徴は以下の5つです。自分に当てはまるものがないかチェックしてみてください。
- 子どもを自分の思い通りにコントロールしようとする
- 過保護・過干渉な関わり方をしてしまう
- 子どもへの期待が過度に大きい
- 友人や親族とのつながりが希薄になっている
- 見捨てられることへの強い不安がある
子どもを自分の思い通りにコントロールしようとする
子離れできない親は、子どもをコントロール下に置こうとします。子どもが危険な目に遭わないよう、行動をなんでも監視したくなってしまう方は多いでしょう。
しかし、監視の目がいきすぎると子どもが自分の意思で判断を下したり行動したりする力が養われません。
子どもを自立した大人へ成長させるためには、いつまでもコントロール下に置き続けないようにしましょう。
過保護・過干渉な関わり方をしてしまう
子どもに対して過保護・過干渉になっていると子離れできません。
我が子を大切に思うあまりに、子どもの持ち物や予定などを必要以上に把握したり管理したり、必要以上に束縛してしまう親は多いでしょう。
しかし、必要以上に関わると子どもは息苦しくなりストレスを感じてしまいます。
子離れするためには関わりたくなる気持ちを我慢し、見守ってあげる姿勢を持ちましょう。
なお、子供との接し方や子育て中に感じるイライラの対処法については、こちらの記事で詳しく解説しているので興味のある方はぜひご覧ください!
子どもへの期待が過度に大きい
子どもへの期待が大きすぎると子離れできません。子どもに対する理想が高いと過度な期待をしてしまいます。
その結果、習い事や勉強を強要してしまい、必要以上の負担を子どもに強いることになりかねません。
親の理想像を押し付けず、子どもの意思を尊重することを心がけましょう。
友人や親族とのつながりが希薄になっている
友人や親族と疎遠になっているのも子離れできない親の特徴です。身近に親しい人がいないと、常に子どものことばかり考えてしまいます。
人間関係が狭い親は、意識を向ける先が我が子しかいないため、子どもの行動に干渉しすぎる傾向にあります。
子どもにしか意識を向けられない状況では、子離れが難しいでしょう。
この場合、我が子以外に興味があることが見つかれば、状況が改善する可能性は大いにあります。
見捨てられることへの強い不安がある
「実家を出た子どもから見捨てられた感じがする」
見捨てられ不安がある親は、このような気持ちを抱いて不安になってしまいます。
見捨てられ不安が原因でいつまでも子どものことを気にかけてしまい、結果として子離れできなくなるでしょう。
見捨てられ不安はカウンセリングによって緩和する可能性があります。
オンラインカウンセリングのKimochなら、プロのカウンセラーによるサポートが受けられるので、興味のある方はぜひお試しください。
親が子離れできないことで生じる問題

子離れできないことで生じる5つの問題を紹介します。
- 子どもに主体性や判断力が育たない
- 失敗や挫折に弱くなる
- 大人になっても親の顔色をうかがう
- 自己肯定感が下がりやすい
- 責任感や自立心が育たない
子どもに主体性や判断力が育たない
子離れできないと、子どもに主体性がなくなります。
子どものことを気にかけるあまり、何でも手伝ってあげたり先にやってあげたりしてしまう方は要注意。
子どもが自分で考える力が身につかず、指示待ちが癖になってしまう恐れがあります。
社会に出てから主体的に動ける人に育てるためには、手助けせずに見守ることも必要でしょう。
失敗や挫折に弱くなる
過保護・過干渉になっていると、子どもは失敗や挫折で心が折れやすくなってしまいます。
親が子どもの行動を決めたり失敗したときの責任を取ったりしているうちは、子どもはあまり傷つきません。
このような状態が続いた後にいざ子離れすると、失敗や挫折を経験したときの立ち直り方がわからず自信を失いやすくなってしまいます。
打たれ強い人間に育てるためには過保護・過干渉にならず、失敗や挫折を経験できる環境を作るのが良いでしょう。
大人になっても親の顔色をうかがう
子離れできずにいると、子どもが大人になっても親の顔色を気にするようになります。
いつも親が身近にいると何をするにも相談したり許可を得たりするため、1人で判断する機会がありません。
そのような状況が続くと大人になっても自分で大きな決断を下せず、いつまでも親に相談する癖がついてしまいます。
自分の人生を自ら切り開ける人になってもらうためには、子離れが欠かせません。
自己肯定感が下がりやすい
子離れできないと子どもの自己肯定感の低下につながります。
子どもは1人立ちすると自分の意思で行動を起こすようになります。その結果、成功体験によって自信が付いたり失敗経験によって打たれ強くなったりするでしょう。
しかし、子離れできないとこのような経験ができず、自己肯定感が低くなってしまいます。
自己肯定感が低いとどのような問題があるのかについては、こちらの記事を参考にしてみてください!
責任感や自立心が育たない
責任感が育たないことも問題です。子離れせずに子どもが自ら物事を判断しないと、自分の言動に責任を持つ経験ができません。
責任感が育っていないと、大人になってからも他人に判断を委ねて自分の意思で行動できなくなるでしょう。
責任感のある人に育てるためには、親が何でも決めずに子どもに意思決定させることが必要です。
親が子離れできない原因

親が子離れできない3つの原因を解説します。
- 精神が安定していない
- 自分の親も子離れできていなかった
- 親からの愛情を受けずに育てられた
- 空の巣症候群などライフイベントの影響
精神が安定していない
精神が安定していないと子離れできません。
子育てする親は以下の理由で精神が不安定になることがあります。
- 育児で家にこもって他人と接する機会がない
- 夫婦関係が良くない
このように人間関係がうまくいっていないと、子どもに心の拠り所を求めて子離れできなくなるでしょう。
自分の親も子離れできていなかった
親が子離れできていなかった場合、自分の子どもに対しても子離れできなくなることは珍しくありません。
なぜなら子育てをするとき、自分がどのように育てられたのかを参考にするからです。
その結果、子離れできないような育て方が正しいと思い込んだり、そもそも子離れできていないことに気づいていなかったりします。
親の育て方が必ずしも正しいとは限らないので、束縛が強い育てられ方をした方は同じような育て方をするのは避けましょう。
親からの愛情を受けずに育てられた
親からの愛情を受けずに育てられた場合も、子離れできない恐れがあります。
子離れできない親に育てられたケースとは逆に、無関心な親に育てられた反動で子どもを大切しようとする気持ちが強くなるでしょう。
その結果、過剰に愛情を注いで子離れできないことがあります。
空の巣症候群などライフイベントの影響
子どもが巣立つことで生じる「空の巣症候群」も、子離れできない原因のひとつです。
子どもと離れることで孤独や喪失感を感じ、過干渉や過保護になりやすくなります。親自身が趣味や友人関係を充実させることで、心理的負担を軽減できます。
子離れできない親が意識すべきこと・改善方法

子離れするために親が意識すべき4つのことを紹介します。
- 子どもと親は違う人間であることを理解する
- 子どもの立場や気持ちを尊重する
- 子どもを信じて任せる
- 趣味や仕事など子ども以外の対象に意識を向ける
- 必要であれば専門家に相談する
子どもと親は違う人間であることを理解する
子離れするためには、子どもと親は違う人間であることを理解しましょう。
「自分はもっと成績が良かった」
「子どもにも自分と同じスポーツをやってほしい」
このように、過去の自分と比較したり同じ経験をさせようとするケースは珍しくありません。
しかし、いくら我が子といえど自分とは違う人間です。時代背景や生活環境などにより自分とは異なる境遇になることは大いにあります。
自分の理想像を押し付けず、子どもの個性を尊重してあげましょう。
子どもの立場や気持ちを尊重する
自分本位ではなく子どもの立場に立って考えることも必要です。
子離れできない親は、子どものことを心配したり自分の理想を求めたりして必要以上に干渉してしまいます。
しかし、子どもの立場に立って考えると過度なコミュニケーションは負担やストレスになることを想像できるでしょう。
不安な気持ちをこらえて見守ってあげることも親の重要な役割です。
子どもを信じて任せる
子離れできないのは、裏を返せば子どもを信用していないということ。子どもの失敗を心配するあまり、つい過保護になってしまいます。
しかし、失敗をしたときにどう対処するか自分で考えると成長につながります。子どものうちからたくさんの失敗を経験できる環境を作ってあげましょう。
趣味や仕事など子ども以外の対象に意識を向ける
子離れするためには、他に興味が湧くものを見つけるのがおすすめです。子育てが生活の大部分を占めていると、常に子どものことばかり考えてしまい子離れできません。
趣味や勉強などに充てる時間を持つと、子どもだけに執着せずに済むでしょう。
子どもが親元を離れた時に喪失感に見舞われないためにも、ぜひ何か興味のあることを見つけてみてください。
必要であれば専門家に相談する
親自身が子離れに苦しむ場合は、カウンセリングや専門家のサポートを受けることも有効です。
心理士や臨床心理士など専門家に相談することで、自分の不安や執着の原因を整理し、実践的な子離れの方法を学ぶことができます。
子どもの立場からできる対処法
子ども側からも、親との距離を適切に保つことは重要です。
大人になった子どもが自立して生活する際に、親の過干渉がストレスになることがあります。以下の方法で、無理なく関係を調整できます。
親との適切な距離感を意識する
毎日の連絡や相談の頻度を自分の生活に合わせて調整し、必要以上に親に気を遣わないようにします。
感情的にならず冷静に気持ちを伝える
親が干渉してきた場合でも、感情的にならず「自分はこうしたい」という意見を丁寧に伝えることが大切です。
必要に応じて第三者やカウンセラーを頼る
親子関係がこじれそうな場合は、家族カウンセリングや第三者の助けを借りることで、互いに無理のない関係を作れます。
子離れできないことでお悩みならオンラインカウンセリングのKimochiがおすすめ

「子離れするタイミングがわからない」
「子育てに関するアドバイスが欲しい」
このように子育てについて悩んでいる方にはオンラインカウンセリング「Kimochi」がおすすめ。
Kimochiには国家資格を持つカウンセラーが在籍しており、抱えている悩みと相性の良いカウンセラーを紹介してくれます。
子離れのような子育ての悩みだけでなく、夫婦関係など家庭に関する問題に対しても幅広く相談に乗ってくれます。
初回は無料でカウンセリングを受けられるため、少しでもお悩みを抱えている方は気軽に相談してみてください。
まとめ
子離れするためには、自分本位にならないことが重要です。いつまでも子どもを管理していては自立した大人には育ちません。
本記事を参考に、子どもが社会に出てから力強く生きていけるよう子離れの第一歩を踏み出しましょう。