近年、「アダルトチルドレン」という言葉がメディアや書籍で注目を集めています。
もともとはアルコール依存症の家庭で育った子どもたちを指す言葉でしたが、今では親の過干渉やDV、機能不全な家庭環境で育ち、大人になってもその影響から生きづらさを感じる人々を広く含む概念として使われるようになりました。
本記事では、アダルトチルドレンの基礎知識から原因、症状・特徴、克服方法、カウンセリングまで、専門家の視点も交えながらわかりやすく解説していきます。
アダルトチルドレンとは?

ここでは「アダルトチルドレン」という用語がどのように生まれ、社会に広まっていったのかを紹介します。
言葉の歴史を知ることで、問題の背景やスコープを正しく把握できるようになります。
アダルトチルドレンの用語や起源・歴史的背景
「アダルトチルドレン(Adult Children)」という言葉は、もともとアルコール依存症の親を持つ子どもを指す専門用語として誕生しました。アメリカの自助グループ活動「ACOA(Adult Children of Alcoholics)」が広まり、その中で使われていた言葉が徐々に一般にも知られるようになったのが始まりとされています。
なぜアダルトチルドレンが広く知られるようになったのか
アルコール依存症の家庭だけでなく、DVやネグレクト、過干渉など、さまざまな形で「機能不全」を抱える家庭があることが社会的に認知されるにつれ、「アダルトチルドレン」という言葉がより広範な問題を捉える言葉として扱われるようになりました。SNSやインターネットの普及により、自分の生きづらさが「アダルトチルドレン」に当てはまるかもしれないと気付き、情報を求める人が増えたことも普及を後押ししています。
アダルトチルドレンの意味
この章では、「機能不全な家庭」というキーワードを切り口に、アダルトチルドレンが形成されるメカニズムと、大人になっても影響が続く理由を解説します。
機能不全な家庭環境(アルコール依存、DV、過干渉など)との関係
アダルトチルドレンとは、文字通り「大人になった子どもたち」のことです。ただし、ここでいう「子ども」とは年齢ではなく、心理的な観点を指しています。
- 親がアルコール依存症や薬物依存症だった
- 家庭内暴力(DV)や言葉の暴力が日常的にあった
- 過干渉や過度な期待、否定的な言葉にさらされた
- 親の不在や育児放棄(ネグレクト)があった
こういった家庭環境で育つと、健全な愛着形成や自尊感情が育ちにくく、大人になっても人間関係や自己肯定感に影響が残ることが多いのです。
どのようにして大人になっても影響が残るのか
機能不全な家庭で育った子どもは、幼少期に身につけた「他者を疑わなければいけない」「自分は大切にされない」といった思い込みを、大人になっても無意識のうちに持ち続けがちです。
以下のような苦しみを抱えやすくなります。
- 対人関係に過度の不安を抱える
- 自分自身を過小評価する
- 親密な関係を築くのが怖い
- 感情コントロールが難しい
アダルトチルドレンの原因

アダルトチルドレンは特定の1つの要因から生まれるわけではなく、さまざまな要因が複合的に作用します。
ここでは代表的な原因を5つに分けて解説します。
1. アルコール依存や薬物依存の家庭
親がアルコール依存症や薬物依存症だと、家庭内のコミュニケーションや金銭管理、情緒的な安定が保たれません。子どもは常に不安定な状態で育ち、自己肯定感や基本的な安心感を得にくくなります。
2. DVや虐待がある家庭
身体的・精神的暴力が蔓延する家庭では、子どもは「いつ暴力が向けられるかわからない」という恐怖の中で生活します。愛情や安心感よりも生存の危機を意識することが多く、心身ともに傷つきを抱えるケースが多いです。
3. 過干渉・過度な期待
一見すると「愛情深い親」にも思えますが、子どもの自主性や人格を尊重せず、過度に管理・支配する家庭もアダルトチルドレンを生みやすい環境と言えます。子どもは自分の意思や感情を抑圧し、「親の望む自分」を演じる傾向が強まります。
4. 親の不在や育児放棄(ネグレクト)
親の仕事や家庭事情などで育児が十分に行われない場合、子どもは必要な愛情やケアを受けられません。結果として、他者への不信感や孤独感を強く抱え、対人関係に苦手意識を持ちながら成長してしまいます。
5. 親自身がアダルトチルドレンである
親自身が愛着障害やアダルトチルドレンであり、その影響が次世代に受け継がれてしまうケースもあります。親が自分の心の傷を癒やすことなく子育てをすると、同じパターンが繰り返されることが多いのです。
アダルトチルドレンの症状・特徴
ここでは、アダルトチルドレンとして育った人が大人になってから感じやすい心の傾向や行動の特徴をご紹介します。<br><br> まず大切なのは、アダルトチルドレンは「病気」や「障害」ではなく、生きづらさにつながる“心の特性”であるということです。
家庭環境の中で身につけざるを得なかった考え方や行動パターンが、大人になった今でも無意識のうちに続く結果、人間関係や自己評価に影響が出ている状態を指します。
「これは私のせいだ」と責める必要はありません。今の自分の状態を知り、少しずつ向き合っていくことで、心の負担を減らし、より自分らしく生きるための一歩を踏み出すことができます。
1. 自己否定感・低い自尊心
「どうせ自分なんか」「私は価値がない」という思い込みを強く抱いてしまい、挑戦や自己主張に対して強い恐怖を感じることがあります。
2. 対人関係の困難
他者からの評価や反応に敏感で、「嫌われたくない」「見捨てられたくない」という不安が強く、適度な距離感を保つのが難しい傾向があります。
3. 感情コントロールの難しさ
自分の感情を適切に表現する方法を学べなかった結果、怒りや悲しみが抑えきれず爆発する、逆にまったく表に出せず鬱々と抱え込むなど、両極端に陥りがちです。
4. 完璧主義・過度の責任感
失敗を極端に恐れ、自分にも周囲にも高い基準を課してしまいます。また、家族を支える「しっかり者」としての役割を背負い込みやすいのも特徴です。
5. 境界線(バウンダリー)の不明確さ
「NO」と言うことに罪悪感を感じやすく、相手に合わせすぎたり、自分のプライベート領域を侵食されたりしても気づかないまま我慢を続けることがあります。
アダルトチルドレンと愛着障害

愛着障害はアダルトチルドレンの核といえる概念です。
安全基地が形成されないことで起こる心の働きを整理し、両者の関係を紹介します。
愛着障害とは?
愛着障害(Attachment Disorder)は、乳幼児期に「安全基地」となる養育者から一貫した愛情や適切な応答を得られなかったことで、対人信頼や自己肯定感が十分に育まれず、成長後も人間関係や情緒の安定に深刻な影響が残る状態を指します。代表的には下記の2型に大別されます。
| タイプ | 表れやすい行動例 | 育った環境の例 |
|---|---|---|
| 反応性愛着障害(RAD) | 情緒反応が乏しい、他者への関心が薄い ・人との関わりを避けがち ・感情をあまり出さない | ・親がほとんど関わってくれなかった ・何度も預け先が変わった |
| 脱抑制型愛着障害(DSED) | 見知らぬ人にも過度に親密に接近する ・初対面でもすぐになつく ・距離の取り方が苦手 | ・決まった人と過ごす時間が少なかった ・親がいつも忙しかった |
愛着障害の根底には「自分は大切にされないかもしれない」という深い不安があります。
そのため、成人後は親密さを避ける(回避型)かしがみつくように他者へ依存する(不安型)という両極端な対人パターンを取りやすく、結果として人間関係が不安定になりがちです。
アダルトチルドレンの多くは、この未解決の愛着課題を抱えていることが臨床的にも示されています。
愛着形成との関係性
アダルトチルドレンの多くは、子ども時代に 安定した愛着を築くことができなかったという共通点を持っています。
愛着とは、「自分が困ったとき、誰かが助けてくれる」という安心感や信頼の気持ちを育てることです。
この安心感は、親や養育者との関係を通じて自然と身についていくものですが、機能不全な家庭ではそれがうまく育たないことがあります。
たとえば、次のような状況では愛着が安定しづらくなります。
- 親がいつもイライラしていて、顔色をうかがう日々だった
- 甘えたくても「泣くな」「我慢しなさい」と感情を否定された
- 急に怒られたり、無視されたりして、どう接すればよいか分からなかった
このような経験が続くと、子どもは「本音を出すと嫌われる」「人は信じられない」という思いを心の奥に抱えて成長します。これがアダルトチルドレンの「人間関係の不安定さ」や「自己肯定感の低さ」につながっていくのです。
愛着の問題は、決して本人のせいではありません。けれど、今からでも少しずつ「人を信じる力」や「自分の感情を大切にする力」は育て直すことができます。
その第一歩が、自分の過去を知り、向き合おうとすることです。
とはいえ、自分ひとりでその作業をするのは、怖さや不安もあるかもしれません。
オンラインカウンセリング「Kimochi」では、公認心理師の資格を持つカウンセラーが、あなたのペースに寄り添いながらお話を伺います。
「うまく言葉にできないかも…」
「どこから話していいか分からない…」
そんな気持ちがあっても大丈夫です。誰にも話せなかった思いや、不安な気持ちも、Kimochiなら安心して相談することができます。
アダルトチルドレンの種類

アダルトチルドレンといっても、すべての人が同じような行動をするわけではありません。家庭の中で無意識に引き受けてきた「役割」によって、いくつかのタイプに分けられることがあります。
ここでは、代表的な6つのタイプを紹介し、それぞれの特徴と背景にある心の動きを解説します。
| 名前 | 主な特徴 | 育った環境 | 心の背景(心理状況) |
|---|---|---|---|
| ヒーロー型 | 優等生タイプ。 責任感が強く、完璧を目指す | 親が不安定/家族を支える役割を担っていた | 賞賛されることで存在価値を感じようとする |
| スケープゴート型 | 反抗的・問題児と見られる行動が多い | 家庭に怒りや不満が多い | 自分が悪者になることで家族のバランスを保つ |
| ロストチャイルド型 | 目立たず静か。 引きこもりやすい | 家庭に関わりたくない雰囲気があった | 「いないふり」でトラブルを避けていた |
| マスコット型 | 明るくおどける。 ムードメーカー役 | 家庭に緊張や重苦しさがあった | 笑いで空気を和らげ、本音を隠してきた |
| ケアテイカー型 | 人の世話を焼き、頼られることに安心する | 親の感情に振り回されていた | 尽くすことで愛されようとしていた |
| プラケーター型 | 対立を避け、周囲に合わせすぎる | 家庭内に争いが多かった | 「自分が我慢すれば平和」と信じていた |
1. ヒーロー型(家庭の中のしっかり者)
- 成績や仕事など、何事にも「完璧」を目指しやすい
- 小さい頃から「いい子」としてふるまってきた
- 家族や周囲からの期待に応えようとがんばりすぎる
ヒーロー型の心の背景(心理メカニズム)
家の中が混乱していたり、親が安定しない状況の中で、子どもながらに「自分がしっかりしなきゃ」と感じて育ったタイプです。賞賛されることで自分の価値を感じようとしますが、内側ではプレッシャーや孤独を抱えていることも多いです。
2. スケープゴート型(家庭の中の悪者役)
- 怒られたり注意されたりすることが多い
- 学校や社会でのトラブルを繰り返すこともある
- 問題行動や反抗的な態度をとりがち
スケープゴート型の心の背景(心理メカニズム)
家庭の中のストレスや怒りを一手に引き受ける「はけ口」となり、無意識に悪目立ちするような行動を取ることで、家族のバランスを保とうとします。表面的には「問題児」ですが、実は深い寂しさや自己否定感を隠していることが多いです。
3. ロストチャイルド型(見えない子ども)
- 存在感が薄く、あまり目立たない
- 自分の気持ちを表に出さず、ひとりの世界に閉じこもる
- 集団の中でも「いないふり」をしてしまうことがある
ロストチャイルド型の心の背景(心理メカニズム)
家庭内のトラブルに巻き込まれないよう、静かにやり過ごすことで自分を守ってきたタイプです。小さい頃から「目立たないようにしよう」「邪魔にならないようにしよう」と考えていたことが、無表情や引っ込み思案といった性格につながることがあります。
4. マスコット型(家族のムードメーカー)
- 冗談を言ったりふざけたりして場を明るくしようとする
- 人を笑わせるのが得意で、「明るい人」と思われがち
- でもひとりになると急に落ち込むこともある
マスコット型の心の背景(心理メカニズム)
家庭内の空気が重いときに、なんとか雰囲気を軽くしようと「笑い」や「おどけ」を使って自分の役割を果たしてきたタイプです。しかし、その裏で自分のつらさや寂しさを見せられず、心の中にたくさんの感情を押し込めてしまっていることがあります。
5. ケアテイカー型(世話焼き役)
- 人の気持ちに敏感で、つい面倒を見てしまう
- 頼られると断れず、無理をしてでも相手を助けようとする
- 自分のことよりも他人を優先しがち
ケアテイカー型の心の背景(心理メカニズム)
本来は親が子どもにするべきサポートを、逆に自分が親にしていた経験のある人が多いです。「お母さんが泣かないように」「家族が壊れないように」と、幼い頃から家族の感情を背負ってきた結果、大人になっても“人の世話をすること=自分の価値”と思い込んでしまいます。
6. プラケーター型(平和主義者)
- 争いごとが苦手で、いつもその場をおさめようとする
- 自分の意見を言うのが怖くて、他人に合わせてしまう
- 人の顔色ばかり気になり、本音を言えない
プラケーター型の心の背景(心理メカニズム)
家族の中で「ケンカや怒り」が頻繁だった場合、無意識に「自分が黙っていれば平和になる」と考えてきたタイプです。その結果、大人になっても人に合わせすぎたり、自分の感情や希望を押し殺してしまう傾向があります。
これらのタイプはあくまで「傾向」であり、1人の中に複数の特徴が混ざっていることもよくあります。
大切なのは、「なぜ自分がこうなったのか」を責めるのではなく、「そうせざるを得なかった自分」を少しずつ理解し、ねぎらってあげることです。
アダルトチルドレンを克服する方法
アダルトチルドレンとしての生きづらさは、過去の家庭環境や経験から生まれたものです。過去を変えることはできませんが、「今」から自分の考え方や行動を見直すことで、少しずつ回復していくことは可能です。
ここでは、克服のための5つのステップを紹介します。自分に合うところから、少しずつ取り入れてみましょう。
1. 自己理解とインナーチャイルドワーク
まずは、自分が抱えている傷や思い込みに気づくことが回復の第一歩です。
心の中にいる「傷ついた子ども(インナーチャイルド)」の存在を認め、「つらかったね」「よくがんばってきたね」と声をかけるようなイメージで、自分自身をいたわることが大切です。
過去の体験を見つめ直すことで、今の自分の行動パターンや考え方の背景が見えてきます。
2. 感情表現の練習
アダルトチルドレンの多くは、子どもの頃から感情を我慢することに慣れてしまっています。
怒り・悲しみ・喜びなど、どんな感情も「感じてもいいもの」として少しずつ表現する練習をしましょう。
具体的には、日記に書く・信頼できる人に話す・安心できる場で感情を吐き出すなどの方法があります。
感情にフタをするのではなく、「感じて、伝えても大丈夫だった」という体験が、心を少しずつ自由にしていきます。
3. 境界線(バウンダリー)の確立
「NOと言えない」「人に合わせすぎて疲れる」といった悩みを持つ方は、自分と他人の境界線があいまいになっていることが多いです。
自分の気持ちや限界を大切にし、「それはできません」「今は休みたいです」と伝える練習を少しずつ始めてみましょう。
相手との距離を適切に取ることで、自分を守り、自分らしく過ごせる時間が増えていきます。
4. ポジティブな対人関係の構築
これまでの経験から「人は信用できない」「いつか裏切られる」と感じている人も少なくありません。
しかし、すべての人がそうではないということを、少しずつ体験を通して知っていくことが回復につながります。
自分を大切にしてくれる人、気持ちを尊重してくれる人との関係を築き、「人といても安心できる」という感覚を取り戻していきましょう。
5. 専門家や自助グループのサポート
一人で抱え込まず、第三者の力を借りることもとても有効です。
公認心理師などの専門家によるカウンセリングでは、自分の思考や感情を整理し、安全な場で本音を話すことができます。
また、自助グループ(アダルトチルドレン当事者の集まり)に参加すると、「同じ悩みを持つ人がいる」と感じられ、孤独感が和らぐ効果もあります。
安心できるつながりがあることで、少しずつ心の回復が進んでいきます。
アダルトチルドレンとカウンセリング

アダルトチルドレンとしての苦しみを抱えながらも、「誰かに相談するのがこわい」「自分のことを話すのはハードルが高い」と感じる方は少なくありません。
無理もありません。これまで「自分の気持ちをわかってもらえなかった」「話しても否定された」経験があると、人を頼ること自体が怖くなってしまうからです。
でも、そんなあなたにこそ伝えたいのは「話すことで、初めて分かることがある」ということです。
心の中にあるものを少しずつ外に出すことで、心が軽くなり、少しずつ回復の道が開けていきます。
カウンセリングの種類と特徴
アダルトチルドレンの悩みに対応できるカウンセリングには、いくつかの方法があります。ここでは代表的な3つをご紹介します。
- 認知行動療法(CBT)
ネガティブな思い込みや反応パターンに気づき、それを少しずつ修正していく療法です。
「自分はダメな人間だ」「人に迷惑をかけてはいけない」といった考えが強い人におすすめです。 - 来談者中心療法
カウンセラーがあなたの気持ちを否定せず、共感をもって受けとめることで、自己肯定感を育てることを目的とした療法です。
「ただ気持ちを聞いてほしい」「まずは安心して話せる場所がほしい」という方に向いています。 - 家族療法
家族全体をひとつの「関係性のシステム」として見直すことで、問題の根本を見つけ出し、関係の修復をはかる療法です。
親やきょうだいとの関係に悩んでいる方に効果的です。
専門家に相談することのメリット
専門家との対話では、あなた自身では気づかなかった思考や感情のクセ、過去の経験とのつながりが見えてくることがあります。
たとえば、「人との距離がうまく取れないのは、自分のせいだと思っていたけれど、実は過去の家庭環境が影響していたんだ」といった気づきが得られることも少なくありません。
自分を責めるのではなく、理解するための時間を持つことで、少しずつ自分にやさしくなれるようになります。
アダルトチルドレンの相談ならオンラインカウンセリング「Kimochi(キモチ)」
「誰かに話したいけど、対面で相談するのはちょっと勇気が出ない…」
「忙しくて通う時間がないけど、少しでも心を整理したい」
そんなあなたには、オンラインカウンセリングKimochi(キモチ)をおすすめします。
Kimochiには、アダルトチルドレンや愛着障害の理解が深い、国家資格を持つ公認心理師が多数在籍しています。
スマホやパソコンから、気軽に・安心してカウンセリングを受けることができるため、「初めて相談する方」「過去にカウンセリングでうまく話せなかった方」にも選ばれています。
あなたの過去や苦しみを、誰かが丁寧に受けとめてくれる。
そんな経験を、Kimochiで一緒に始めてみませんか?
まとめ
アダルトチルドレンは、幼少期の家庭環境から生まれた傷や思い込みが大人になっても影響を及ぼす状態を指します。原因や症状は人それぞれですが、共通して「愛着の不足」「自己肯定感の低さ」「対人関係の苦手意識」などが見られます。しかし、適切な自己理解や専門家のサポート、信頼できる対人関係を築くことで、過去の体験に振り回されずに生きられるようになる可能性は十分にあります。
まずは自分の状態や背景に気付くことから始めてみましょう。一人で悩まず、必要に応じてカウンセリングやオンラインサービス「Kimochi(キモチ)」などを活用し、あなたが本来持つ自分らしさを取り戻すきっかけにしていただければ幸いです。
▼あわせて読みたい!アダルトチルドレン(AC)関連記事



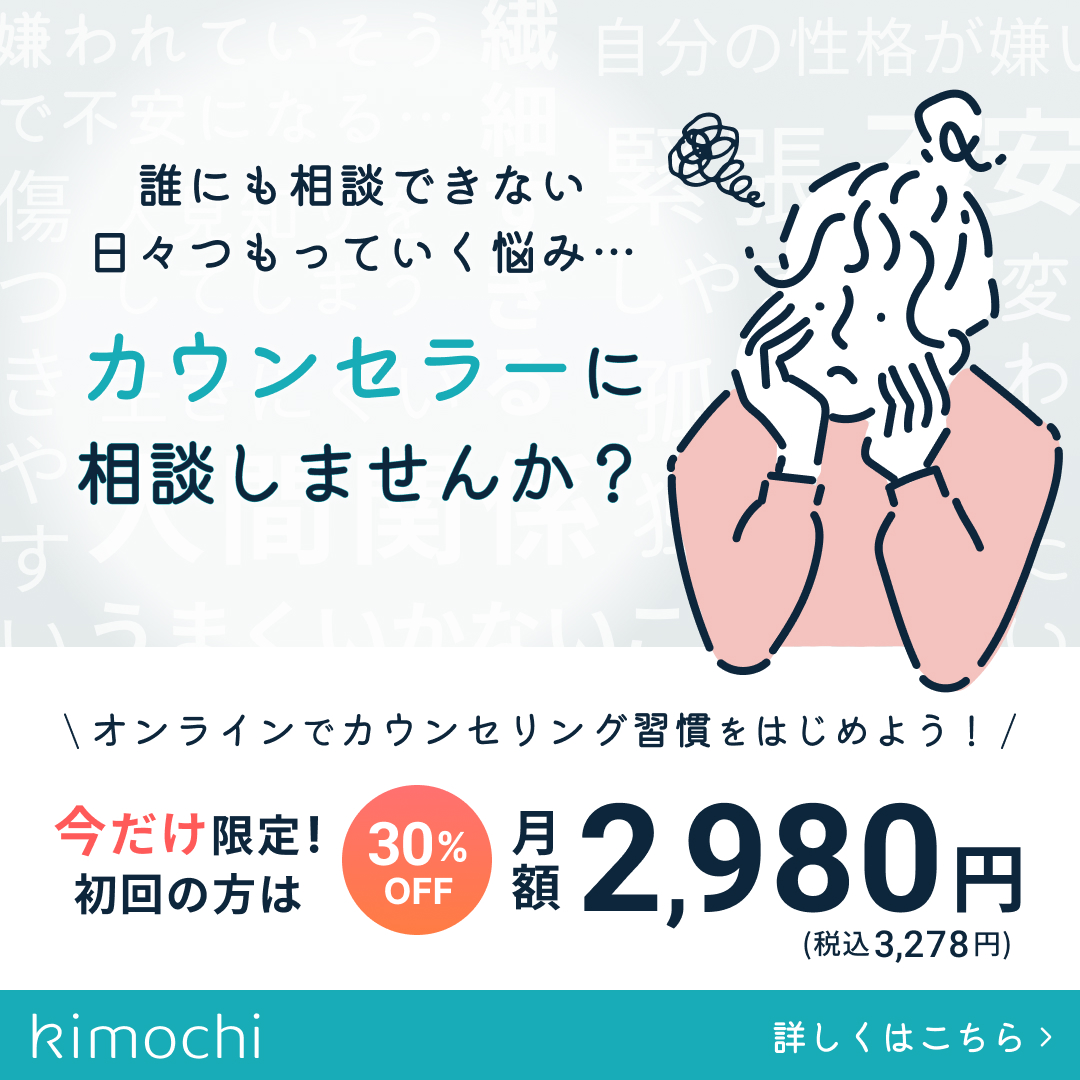
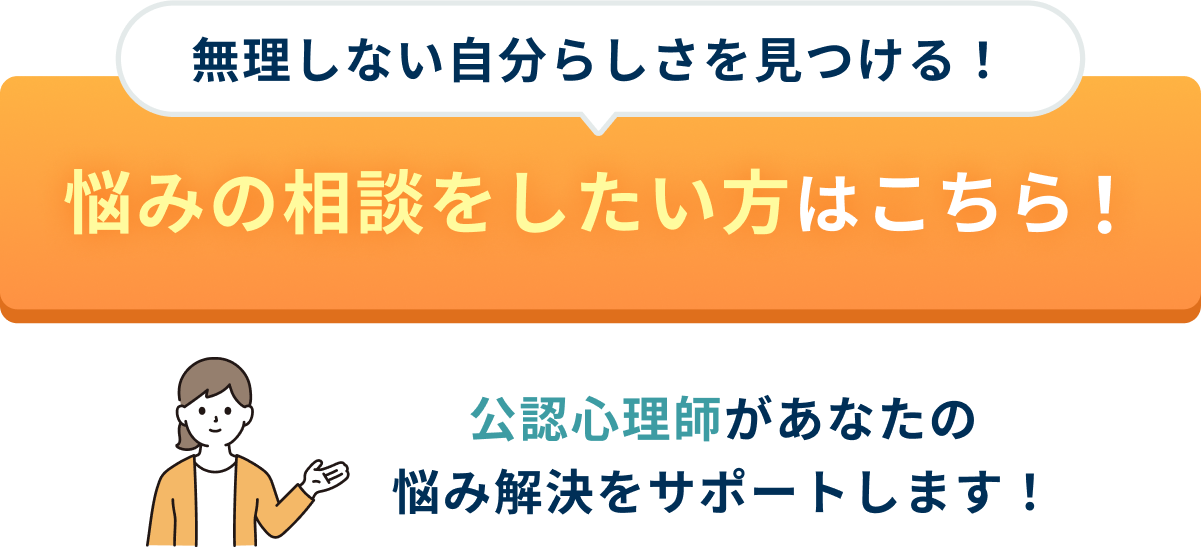
」.jpg)

