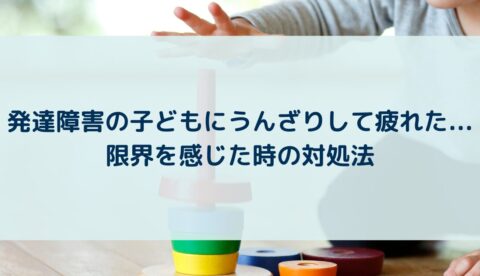お子さまが学校に行けなくなったとき、親として何をしてあげられるのか、自分の対応は正しいのか、悩まれる方は少なくありません。そして、その悩みが長引くことで、気づけばご自身の心が疲れてしまっていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、子どもが不登校になったとき、親としてできることと、親が心身の疲れを感じたときの対処法について、分かりやすくお伝えします。
少しでも、あなたの心が軽くなり、子どもとの関係が穏やかになる一助となれば幸いです。
親が感じる「不登校の現実」とその影響
不登校は、単なる登校拒否や甘えではありません。しかし、そうした誤解や偏見がいまだに根強く、親御さんが周囲から孤立した気持ちになることもあるでしょう。
まずは、不登校という現実に直面したとき、親が感じやすい心理的な負担について整理しておきましょう。
「学校に行かせなければ」という焦りがもたらすプレッシャー
不登校になると、多くの親御さんが「なんとかして学校に戻してあげなければ」と考えます。それはお子さまの将来を思うからこそです。しかし、その焦りが過度になると、無意識のうちに子どもを変えようとするプレッシャーへとつながってしまうことがあります。
このプレッシャーは、子どもにとっても親にとってもストレスの原因となり、悪循環に陥ることもあるため、まずは学校に戻ることだけが正解ではないという意識の転換が大切です。
周囲との比較や視線による孤独感
「○○さんのお子さんは元気に通っているのに…」という声や視線に、必要以上に傷つくこともあるでしょう。比較してしまうこと自体は自然なことですが、それが親自身の無価値感や不安につながると、自尊心を大きく揺さぶります。
大切なのはわが子のペースで進んでいるという確信を持ち、他人軸ではなく親子の軸で考えることです。
理解されにくい「親の苦しさ」の正体とは
不登校になると、どうしても注目は子どもに集まります。しかし、それを支えている親の苦しさは、なかなか見えにくいものです。誰かに打ち明けても「もっと頑張って」と励まされるだけで、心が軽くならなかった経験はないでしょうか。
親自身も「自分がしっかりしないと」と思いすぎてしまい、つらさを口に出すことができないことが、さらに疲れを深めてしまう要因にもなりえます。
子どもにどう向き合う?親が今できる3つの具体的対応
子どもが不登校になったとき、親に求められるのは解決ではなく寄り添いです。ここでは、今すぐできる具体的な対応方法を3つご紹介します。
無理に登校させない「安心の土台づくり」
まず大切なのは、家が安心できる場所であることです。子どもにとって、登校できない理由はさまざま。無理に学校へ戻すことを目的にせず、「家にいてもいい」と伝えることで、子どもの安心感が育まれます。
この土台があるからこそ、子どもは自分の気持ちを少しずつ整理し、次の一歩を考えられるようになります。
子どもの気持ちを引き出す「共感の会話術」
子どもが話してくれるときには、アドバイスよりも共感を優先しましょう。
「そう思ったんだね」「つらかったね」といった受け止めの言葉は、子どもが自分の気持ちを否定されずに受け入れられたと感じる助けになります。
重要なのは、話してくれたことに感謝する気持ちです。会話の主導権を握らず、自然に耳を傾ける姿勢が信頼関係を育てます。
生活リズムを整える「家庭内でできる環境調整」
登校しない日々が続くと、生活リズムが乱れがちです。朝起きる時間や食事の時間を一定に保ち、昼夜逆転を防ぐよう意識しましょう。
決して厳しく管理する必要はありません。小さな習慣の積み重ねが、子どもの心と体の安定につながります。
「疲れた…」と感じた親自身の心のサインに気づく
子どもを思うあまり、自分の限界に気づけない親御さんは少なくありません。ここでは、心の疲労に早く気づくためのサインと、その背景についてご紹介します。
我慢しすぎる人が見落としやすい心のSOS
「まだ頑張れる」「私が弱音を吐くなんて」といった思考に縛られていませんか?
実は、我慢強い人ほど、心が悲鳴を上げていることに気づきにくい傾向があります。
寝つきが悪い、頭が重い、涙が出やすいなどの変化は、心のSOSの可能性があります。
無意識のうちに疲れを溜め込む親の特徴
「子どもの前では笑顔でいなければ」と思い込んでいる親御さんほど、無意識のうちに疲労が蓄積しやすくなります。
他者の期待や理想像にとらわれすぎず、まずは素の自分を認めることが大切です。
頑張りすぎない姿勢こそ、親子関係を保つ鍵
疲れているときこそ、「少し休んでもいい」と自分に言ってあげてください。親が健やかでいることが、結果的に子どもにとっても大きな安心につながります。
親の疲れを和らげるための具体的なセルフケア
では、心身が疲れ切ってしまう前に、どんな対策ができるのでしょうか。すぐに実践できるセルフケアの方法をご紹介します。
ひとり時間の確保と心を休めるルーティン
たとえ10分でもいいので、自分だけの時間を意識的につくってみてください。
好きな香りの中でコーヒーを飲む、静かな音楽を聴く、短い散歩をするなど、小さな習慣の積み重ねが、心の回復を助けてくれます。
誰かに話すことで得られる心のゆとり
家族や友人に気持ちを話すだけで、驚くほど気持ちが軽くなることもあります。
「どう思われるか」より、「今の自分を知ってもらうこと」に意識を向けてみましょう。
SNSや体験記に頼りすぎない情報の取り扱い方
似たような体験談は心強い一方で、「あの人はうまくいっているのに」と焦りにつながることもあります。SNSとは適度な距離を保ち、自分の状況を軸に考えるよう心がけましょう。
長期戦に備えるために活用すべき外部リソース
不登校は短期的に解決するものではありません。だからこそ、信頼できる外部の支援を取り入れることが、親の負担を減らすカギになります。
教育委員会やフリースクールの相談窓口
お住まいの自治体や学校に設置されている教育相談室では、個別の事情に応じたアドバイスが受けられます。また、フリースクールは、学校以外の学びの場としての選択肢です。
同じ悩みを持つ親のピアサポート・地域の会
同じ立場の親同士だからこそ分かり合えることがあります。話すことで、「自分だけじゃない」と感じられるのは、大きな安心になります。
オンラインでも受けられる専門的支援の選択肢
対面が難しい場合でも、今ではオンラインでカウンセリングや相談が受けられるサービスが充実しています。忙しい方や外出が難しい方にもおすすめです。
まとめ|あなたの心も、大切にしていい
子どもが不登校になると、親の心は揺れ動き、先の見えない日々に不安を感じることもあるかもしれません。それでも、子どもを支え続けようとするあなたの姿勢は、かけがえのないものです。
でも、誰かを支えるには、まず自分自身が満たされていることが必要です。
「少し疲れてしまった」「誰かに話を聞いてほしい」と感じたときには、自分の心の声に耳を傾けてあげてください。
もし、誰かに話したい」と思ったときは
オンラインカウンセリング「Kimochi」で、ひと息つきませんか?
専門カウンセラーがあなたに寄り添います。自分の心に優しくする時間が、家族全体の笑顔につながるはずです。