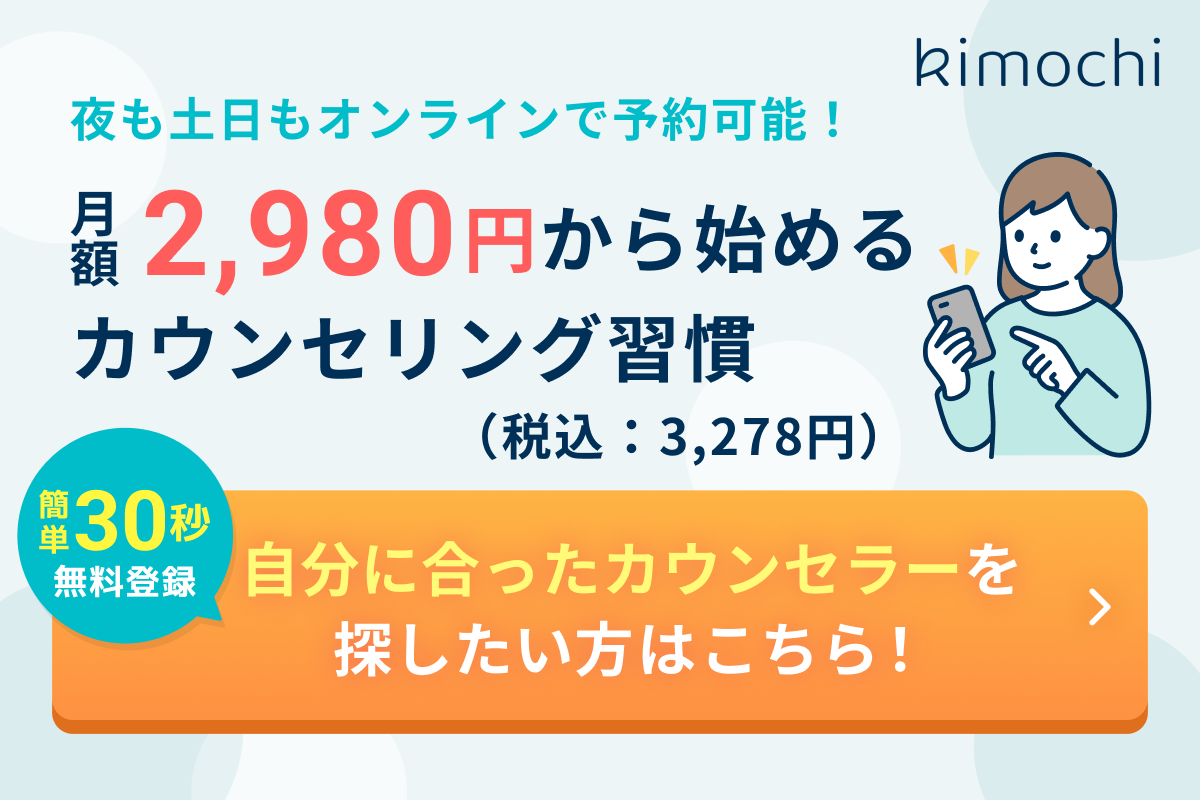「また怒ってしまった…」
「子どもは悪くないのに、私が勝手にイライラしてしまった」
「なんでこんなに余裕がないんだろう…」
こんなふうに、日々の育児のなかで自分を責めてしまうこと、ありませんか?
子どもを大切に思っているのに、そんな自分に対する罪悪感や自己嫌悪は、親としての心を深く傷つけます。
でもそれは、あなたがダメだからではありません。この記事では、子育て中のイライラや自己嫌悪の原因と現実的かつやさしい対策をご紹介します。
こんなとき、ありませんか?
寝かしつけた直後に泣かれて、つい怒鳴ってしまった
ようやく寝かしつけに成功したと思ったら、数分後にまた泣き出した。
「なんで今なの!?」「もう勘弁して…」とイライラが爆発し、子どもにきつくあたってしまった。
その直後、我に返って自己嫌悪に襲われることは多くの親が経験する典型的なエピソードです。
SNSの「いいお母さん」に落ち込む夜
インスタやブログで見る理想的な育児風景。笑顔でお菓子作り、手作りの知育遊び、整ったリビング。
それに比べて、自分はイライラしてばかりで、テレビに頼りっぱなしで、家は散らかっている。
他人の「一瞬」と自分の「全体」を比べてしまい、自信をなくしていませんか?
子どもが寝たあと、自己嫌悪で涙が出る
「本当はもっと優しくしたかった」
「怒鳴るんじゃなくて、話を聞いてあげればよかった」
静かな夜、寝顔を見るたびに胸が痛む。そんな育児のあと悔しさを抱えて、涙を流す日もあるかもしれません。
なぜそんなにイライラしてしまうの?原因を解説
ホルモンバランス・睡眠不足など身体の問題
育児中の身体は、常に戦闘モードです。
産後のホルモン変化、慢性的な睡眠不足、食事の偏り、運動不足などの積み重ねが、自律神経のバランスを乱し、ちょっとした刺激にも過敏に反応してしまいます。
感情の爆発ではなく、身体からの悲鳴であることも少なくありません。
「こうすべき」という理想の親像に縛られている
「ちゃんとしたごはんを作らなきゃ」
「いつも笑顔でいなきゃ」
「子どもを叱らず、話して聞かせるのが正解」
こうした理想の親像が、自分を無意識に追い詰めることがあります。完璧でいようとするあまり、小さなつまずきにも強く反応してしまうのです。
育児がうまくいかないのではなく、完璧を求めすぎている
「子どもがぐずった=自分の育て方が悪い」
「うまく対応できない=親失格」
そう思い込んでいませんか?
実際には、育児とはうまくいかないことが前提の活動です。けれど、真面目で責任感の強い人ほど、「育児も仕事のように成果を出さなきゃ」と思い詰めてしまう傾向があります。
ワンオペ・孤立・相談できない環境
話を聞いてくれる人がいない。頼れる家族がいない。パートナーは仕事で不在。
このような育児をひとりで抱え込む状況では、どんなに頑張っていても、限界がきます。人とのつながりが断たれたとき、自己評価はどんどん下がってしまいます。
「怒り」や「自己嫌悪」は悪いもの?
怒りは自分を守るための自然な反応
怒りは「ダメな感情」ではありません。
心理学では、怒りは「自分の大切な価値観が脅かされたとき」に生まれると言われています。
つまり、怒るのはあなたが真剣に向き合っている証拠でもあるのです。
自己嫌悪は「よりよくなりたい」という気持ちの裏返し
「また怒ってしまった…」という気持ちは、自分を責めたいからではなく、「もっといい親でいたい」「子どもといい関係を築きたい」という願いがあるからこそです。
自己嫌悪は、変わりたいという前向きな心のサインでもあります。
感情そのものを否定するのではなく、扱い方を知ることが大切
怒りも、自己嫌悪も、感じること自体に罪はありません。
大切なのは、その感情にどう向き合うか、どう扱うかです。感情を「悪」とせず、受け止めてから行動を選ぶことで、ぐっとラクになります。
今すぐできるイライラ・自己嫌悪への対処法
「思考の反芻」をやめる:未来志向の言い換え練習
「なんであんな言い方しちゃったんだろう」
「やっぱり私って母親に向いてないかも」
そんな思考の堂々巡りには、言い換えが効果的です。
たとえば、「また怒ってしまった」ではなく、「怒るほどつらかった。自分の気持ちも大事にしよう。」
というふうに、未来につながる解釈を選ぶようにしてみてください。
アンガーマネジメント:6秒ルールと呼吸法
怒りがこみ上げたら、まずは深呼吸をしましょう。
怒りのピークは6秒と言われています。その6秒間を深く息を吐きながら耐えることで、感情の衝動に飲まれずにすみます。吸うより吐くを長くがポイントです。
自分にやさしく語りかける「セルフコンパッション」
「そんな自分も仕方ないよ」
「今日もよくがんばったね」
そんなふうに、自分にやさしく語りかける練習をしてみてください。親だからって、いつも強くある必要はありません。
感情の記録をつける
日記に「何があったか」「どう感じたか」「今ならどう対応したいか」などを書き出すと、客観視ができるようになります。
感情と事実を分けて記録することで、自分のパターンや傾向が見えてきます。
ひとりで抱え込まないためにできること
家族・パートナーと「分担」ではなく「共同育児」へ
育児は「分担」するだけでなく、家族みんなで「一緒に育てる」という意識が大切です。
パートナーにお願いするときは、命令口調にならないよう「〇〇してもらえると助かる」と伝えると、協力しやすくなります。お互いの状況や気持ちを尊重しながら、無理なく助け合う関係を築きましょう。
支援サービスや保育の活用
育児は一人で抱え込む必要はありません。
地域の一時保育や家事代行サービスなど、使えるサポートは積極的に活用しましょう。頼るのは悪いことと思わず、休息をとることが自分と子どものために大切です。
孤独を感じたら、誰かに話す勇気をもつ
育児の孤独感は、多くの親が経験します。
信頼できる友人やママ友、地域の相談窓口など、誰かに話すだけでも気持ちは軽くなります。
カウンセラーや心理士に相談することも特別なことではありません。専門家はあなたの気持ちを受け止め、解決策を一緒に考えてくれます。
一人で抱え込まず、話すことで感情を整理し、心の負担を減らしましょう。
まとめ
子育て中のイライラや自己嫌悪は、あなたが子どもと真剣に向き合っている証です。
それだけの愛情があるからこそ、生まれてくる感情です。だからどうか、自分を責めないでください。
感情に振り回される日もあるかもしれません。
けれど、「気づこう」「変わろう」としているあなたは、すでに前に進んでいます。
もし、誰かに話したいと思ったら
ひとりでがんばりすぎていませんか?話すだけで気持ちがラクになることもあります。
オンラインカウンセリング「Kimochi(キモチ)」は、公認心理師などの専門家に、スマホから気軽に相談できるオンラインカウンセリングサービスです。